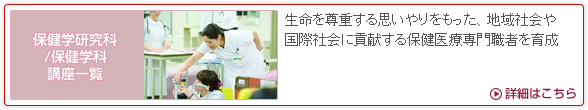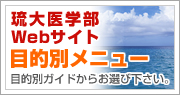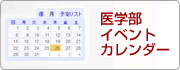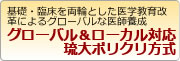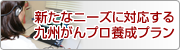保健学科/保健学研究科保健学科・保健学研究科HP
大学院保健学研究科
1968年に沖縄県の保健医療の向上を目指して琉球大学に保健学部が設置されました。保健学部では地域医療を担う看護師や保健師、助産師、養護教諭、臨床検査技師のほか、沖縄県の公衆衛生の向上を支える保健関連の行政職や保健医療分野の大学教員、研究者など多彩な人材を数多く輩出してきました。この保健学部を礎として、1986年に保健学研究科が国立大学2番目の保健学専攻の大学院として設置されました。
保健学研究科は、人間健康開発学と国際島嶼保健学2領域で構成されており、沖縄県の社会文化的環境および亜熱帯性自然環境を基盤とした健康・長寿の維持増進および再生に資する研究や、健康資源の解明に関する研究、アジア・太平洋地域の島嶼・僻地・地域保健の課題とその対策に関する研究などのユニークな研究テーマに取り組んでいます。これら2つの領域は互いに融合し、亜熱帯性自然環境を基盤とした研究から得られた成果は、アジア・太平洋・アフリカ諸国での保健医療の増進に寄与するだけでなく、沖縄における異文化理解の力をもった保健医療者としての人材の育成にも貢献しています。
また、保健学研究科は、グローカルな開かれた研究科として沖縄と海外のフィールドを使った研究や教育が推進され発展しており、英語による教育のコースも設置され留学生と日本人学生がともに学ぶ環境が整っています。保健学研究科の特別プログラム(Okinawa Global Health Science Program)は、JICA(国際協力機構)開発大学院連携プログラムにも登録されており、アジア、太平洋、アフリカ各国から多数の留学生を受け入れています。この受け入れはアジア ・太平洋諸国の多数の研究機関と交流協定を締結し、共同研究を推進していく中で実現したものです。留学生だけでなく日本人大学院生の特別プログラムへの積極的参加をはかることによって相互学習の環境が整っています。保健学研究科修了生は、グローバルヘルスの分野で活躍しています。
保健学科
保健学は、健康に関する科学的な研究や理論を基盤とする実践的学問であり、健康の維持・増進、疾病の予防・管理、生活習慣の改善などに寄与する学問です。看護学、検査学、疫学、栄養学、運動科学、心理学および社会学など、様々な分野が連携し、個人やコミュニティの健康を促進するための知識、技術、解決策やプログラムを開発することを目指します。
現代社会は、少子高齢化における人口減少、大規模災害や生命を脅かす感染症および地政学的リスクなどに伴う様々な健康課題に直面しており、特にCOVID-19の流行や未曾有の自然災害は、保健学を学ぶ者に多くの教訓をもたらしました。つまり、健康問題に取り組む際には、地球規模でのアプローチである「グローバルな視点」、地域の持つ文化、ノウハウ、人のつながりや支え合いなどの社会資源を利用する「ローカルな視点」、また、情報通信技術(ICT)、人工知能 (AI) や医療デジタルトランスフォーメーション (DX)を活用する「デジタル化の視点」が必要であり、これら「3つの視点」を統合した医療人材の育成が求められています。このような医療人材育成をめざし、琉球大学では、500以上の共通教育等科目と、保健学科では、「生命倫理学」をはじめ100以上の専門教育科目が提供されています。また、タイやラオスなどの海外の学生との交流も積極的に行っており、学生の能動的な学習姿勢を期待しています。また、医療従事者や研究者を目指す学生には、幅広い知識や高度な専門技術に加え、豊かな人間性、社会性や高い倫理観も求められます。琉球大学には120を超える部活やサークルがあり、人間形成のために重要な大学4年間を多くの人と交流する機会を得ることができます。
最後に、琉球大学医学部保健学科は、戦後の沖縄県の医療・福祉の復興、特に感染症治療や予防および母子保健の確立のため、1968年に那覇市与儀に保健学部として設置されました。1983年に西原町上原への移転を経て、“国際性・離島の特性を踏まえた沖縄健康医療拠点”形成を目指し、2025年に西普天間へ移転します。沖縄健康医療拠点の形成に向けて、医療イノベーションを推進するために、国際化、人材育成、医療水準の向上、先端研究・産業振興など、様々な取り組みが行われています。本学科を希望する学生の皆様には、その一翼を担い、この目標に貢献できる人材となることを期待しています。