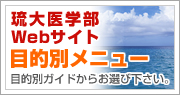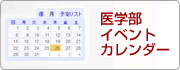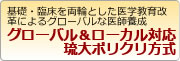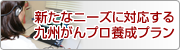医学部長 就任の挨拶
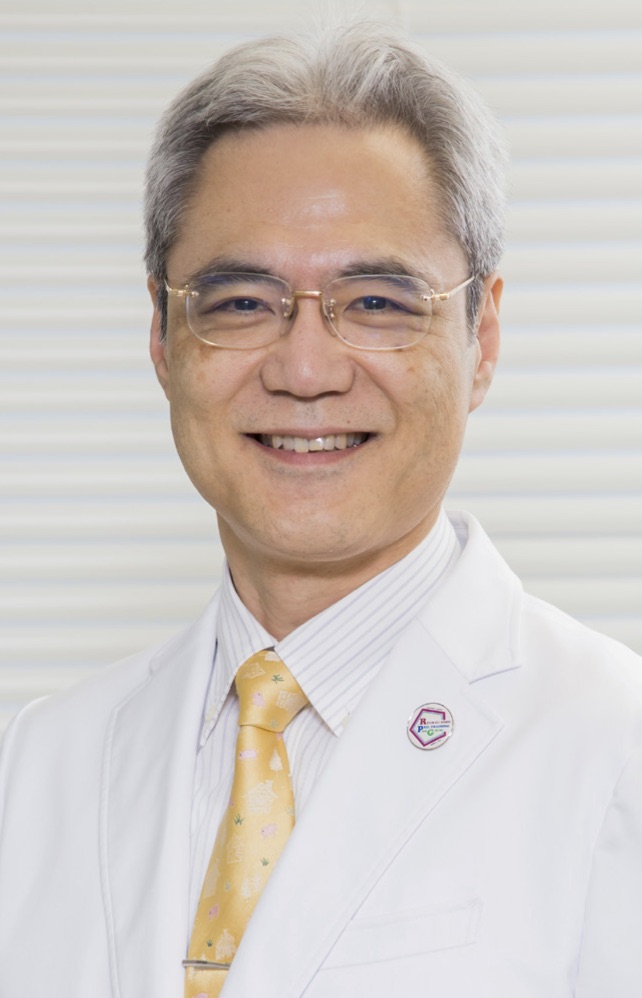
2025年4月1日付けで、医学部長・大学院医学研究科長を拝命いたしました、中西浩一でございます。まず初めに、皆様に心より感謝申し上げるとともに、この新たな任を担うことができましたことを大変光栄に存じます。
1.琉球大学と地域医療の役割
琉球大学は、沖縄の地域社会に密接に結びついた学問の場として、長年にわたり学術と地域貢献の両面において大きな役割を果たしてきました。沖縄という特異な地理的・文化的背景を持つこの地において、医学部・医学研究科の責務は、地域医療の発展に貢献すること、そして地域社会の健康課題に対応することにあります。私たちの活動が地域に深く根ざし、社会に実際の恩恵をもたらすことを、何より大切にしていきたいと考えています。
2.新キャンパスへの移転と教育・研究環境の強化
医学部および病院は、2025年3月までに移転を完了いたしました。新たなキャンパスが宜野湾市西普天間地区に移転したことで、私たちの教育・研究環境が一層充実し、地域医療を支える拠点としての役割を強化できたことを大変嬉しく存じます。移転に伴う施設の設計においては、これまでの経験を生かし、広々とした講義室など、学びの場として快適で機能的な空間づくりを進めています。また、COVID-19への対応を鑑みて、より良い対面・遠隔講義のハイブリッド型教育システムを整備し、学生が心身ともに健康的に学び続けられる環境作りを目指します。
3.医学と保健学の連携強化と教育・研究の充実
医学科・医学研究科と保健学科・保健学研究科との連携を一層強化していく所存です。新しい施設では、医学科・医学研究科と保健学科・保健学研究科が同じ研究棟を共有することとなり、これが物理的にも精神的にも連携の強化を促す大きなチャンスとなります。教育面でも、それぞれの講義を共同で行い、両学科の研究の融合、より先進的な学問領域の開拓を目指していきます。特に地域医療や沖縄特有の健康問題に関する研究は、今後ますます重要となります。そのため、それぞれの特徴を活かし、相互の支援体制を強化していく所存です。
4.医学部の教育の質向上と学生支援
医学部の教育においては、学生一人ひとりが確実に成長できるよう、学びの質をさらに高めていきます。直近の国家試験においては、保健学科の看護師・保健師・助産師の合格率は100%、医学科(96.7%)も素晴らしい成績を収めました。これらの成果は、琉球大学の教育の質の高さを示すものであり、今後も学生の成長を支援する体制を強化していきます。特に、今後の教育はより柔軟で効果的な学びを提供することが求められます。そのため、教師と学生の密なコミュニケーションの機会を増やし、学びの質をさらに高めてまいります。
5.研究の推進と地域医療への貢献
研究面では、今後も沖縄特有の疾病や地域医療の課題に焦点を当てた研究の推進を目指し、外部資金の獲得に力を入れます。沖縄県や地域の医療機関との連携を深めることにより、社会と密接に連携した研究を進めていきます。また、先端医学研究センターの活動をさらに拡充し、全学的な支援体制を整備して、医学研究の最前線を牽引する役割を果たしていきたいと考えています。
6.病院との連携強化と臨床教育・研究の充実
医学部・医学研究科と病院との連携をより強化し、地域医療の質向上に寄与できるよう尽力していきます。医学部と病院が一体となり、患者さんに最適な医療を提供するためには、両者の協力が欠かせません。そのため、臨床教育や研究活動の充実を目指し、病院の医師と連携しながら、より多くの学生が臨床現場で学び、経験を積むことができる体制を整えてまいります。
最後に、琉球大学医学部は、沖縄の地域特性を生かし、地域医療に貢献することを使命として、今後も教育・研究・医療の各分野で発展を遂げていきます。私自身、皆様と力を合わせ、より良い未来を切り開いていくために全力を尽くす所存です。どうぞよろしくお願い申し上げます。
2025年4月1日
琉球大学医学部長・大学院医学研究科長
中西浩一



 皆様、新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり、一言、ご挨拶を申し上げます。昨年の医学部・医学研究科の動向を振り返り、今年の抱負を述べさせていただきます。
1.人事
昨年、医学部・医学研究科に4名の教授をお迎えしました。昨年1月には、医化学講座に東京大学工学系研究科から鈴木健夫教授をお迎えし、昨年5月には、医学教育企画室に「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」実施のための特命教授として、沖縄県立中部病院から金城紀与史先生をお迎えしました。そして、昨年7月には、循環器・腎臓・神経内科学講座に、徳島大学から楠瀬賢也教授を、昨年10月には、女性・生殖医学講座に、新潟大学から関根正幸教授をお迎えしました。
2.教育
昨年の本学の医師国家試験合格率は、新卒が97.6%(全国82校中20位)、新卒+既卒が95.6%(同17位)で、素晴らしい結果でした。また、昨年の看護師、保健師、助産師の国家試験の合格率はすべて100%で、こちらも大変素晴らしい結果でした。一方、昨年の臨床検査技師の国家試験の合格率は71.4%で、全国平均の合格率を少し下回りました。この点については検討の余地がありそうです。また、文科省による補助金等の公募事業においては、一昨年「ポストコロナ時代の医療人材育成拠点形成事業」に採択され、昨年「質の高い臨床教育・研究の確保事業」に採択されました。医学教育モデル・コア・カリキュラムは、令和4年度に改訂され、令和6年度の入学者から適用されます。臨床実習前OSCEとCBTの共用試験は、令和5年度から公的化されました。また、今年11月には、6年ぶり2回目の医学教育分野別評価を受審する予定です。
3.研究
昨年、医学部・医学研究科から沢山の研究成果が発表されました。保健学科国際地域保健学分野の小林潤教授は、Tropical Medicine and Health 2023 (IF 4.3)にEditorとして特集号を企画編集され、その特集号に多国間政策比較やケーススタディー等に関する4報の論文を発表されました。先進医療創成科学講座の山下暁朗教授らの研究グループは、リボソームにおいてタンパク質に翻訳中のmRNAを回収する方法を確立し、タンパク質発現量と密接に相関するmRNA定量法の開発に成功しました(Nucleic Acids Research 2023, IF 14.9)。脳神経外科学講座の石内勝吾教授らの研究グループは、脳悪性腫瘍に対する放射線治療において、高気圧酸素療法とNMDA受容体拮抗薬メマンチン投与を併用すると、放射線治療により引き起こされる正常脳組織の放射線傷害と認知機能低下を予防できることを世界に先駆けて報告されました(Neuro-Oncology 2023, IF 15.9)。医化学講座の鈴木健夫教授らの研究グループは、RNAに糖を付加する糖転移酵素を発見し、その酵素が成長障害に重要な役割を果たしていることを世界で初めて明らかにしました(Cell 2023, IF 64.5)。
4.学生の取組
医療系サークルOff the Clockに所属する医学科の2年次と3年次の6名は、第9回全国医学生BLS選手権大会に参加し総合優勝しました。BLSとはBasic Life Support(一次救命処置=心肺蘇生法)のことで、全国医学生BLS選手権大会は心肺蘇生法の知識と技術を競う大会です。琉球大学は参加した35大学(41チーム)の中で第1位になりました。
5.移転
皆様のご支援・ご協力のおかげで、医学部と病院の宜野湾市西普天間住宅地区跡地への移転事業は順調に進捗しています。医学部関連の建物は、現在約4割が完成しており、令和6年10月末に竣工する予定で、医学部の開学日は令和7年4月1日の予定です。また、病院関連の建物は、現在約9割が完成しており、令和6年6月末に竣工する予定で、病院の開院日は令和7年1月6日の予定です。
最後に、抱負を述べさせていただきます。私の医学部長・医学研究科長の任期は、ちょうど医学部の移転が完了する令和7年3月末までです。移転事業が成功するように、そして医学部・医学研究科がさらに発展するように、今年も精一杯尽力して参ります。今年が、皆様にとって、健康で幸せな一年になることを衷心より祈念申し上げ、私の年頭のご挨拶とさせていただきます。
令和6(2024)年1月4日
皆様、新年明けましておめでとうございます。年頭にあたり、一言、ご挨拶を申し上げます。昨年の医学部・医学研究科の動向を振り返り、今年の抱負を述べさせていただきます。
1.人事
昨年、医学部・医学研究科に4名の教授をお迎えしました。昨年1月には、医化学講座に東京大学工学系研究科から鈴木健夫教授をお迎えし、昨年5月には、医学教育企画室に「ポストコロナ時代の医療人材養成拠点形成事業」実施のための特命教授として、沖縄県立中部病院から金城紀与史先生をお迎えしました。そして、昨年7月には、循環器・腎臓・神経内科学講座に、徳島大学から楠瀬賢也教授を、昨年10月には、女性・生殖医学講座に、新潟大学から関根正幸教授をお迎えしました。
2.教育
昨年の本学の医師国家試験合格率は、新卒が97.6%(全国82校中20位)、新卒+既卒が95.6%(同17位)で、素晴らしい結果でした。また、昨年の看護師、保健師、助産師の国家試験の合格率はすべて100%で、こちらも大変素晴らしい結果でした。一方、昨年の臨床検査技師の国家試験の合格率は71.4%で、全国平均の合格率を少し下回りました。この点については検討の余地がありそうです。また、文科省による補助金等の公募事業においては、一昨年「ポストコロナ時代の医療人材育成拠点形成事業」に採択され、昨年「質の高い臨床教育・研究の確保事業」に採択されました。医学教育モデル・コア・カリキュラムは、令和4年度に改訂され、令和6年度の入学者から適用されます。臨床実習前OSCEとCBTの共用試験は、令和5年度から公的化されました。また、今年11月には、6年ぶり2回目の医学教育分野別評価を受審する予定です。
3.研究
昨年、医学部・医学研究科から沢山の研究成果が発表されました。保健学科国際地域保健学分野の小林潤教授は、Tropical Medicine and Health 2023 (IF 4.3)にEditorとして特集号を企画編集され、その特集号に多国間政策比較やケーススタディー等に関する4報の論文を発表されました。先進医療創成科学講座の山下暁朗教授らの研究グループは、リボソームにおいてタンパク質に翻訳中のmRNAを回収する方法を確立し、タンパク質発現量と密接に相関するmRNA定量法の開発に成功しました(Nucleic Acids Research 2023, IF 14.9)。脳神経外科学講座の石内勝吾教授らの研究グループは、脳悪性腫瘍に対する放射線治療において、高気圧酸素療法とNMDA受容体拮抗薬メマンチン投与を併用すると、放射線治療により引き起こされる正常脳組織の放射線傷害と認知機能低下を予防できることを世界に先駆けて報告されました(Neuro-Oncology 2023, IF 15.9)。医化学講座の鈴木健夫教授らの研究グループは、RNAに糖を付加する糖転移酵素を発見し、その酵素が成長障害に重要な役割を果たしていることを世界で初めて明らかにしました(Cell 2023, IF 64.5)。
4.学生の取組
医療系サークルOff the Clockに所属する医学科の2年次と3年次の6名は、第9回全国医学生BLS選手権大会に参加し総合優勝しました。BLSとはBasic Life Support(一次救命処置=心肺蘇生法)のことで、全国医学生BLS選手権大会は心肺蘇生法の知識と技術を競う大会です。琉球大学は参加した35大学(41チーム)の中で第1位になりました。
5.移転
皆様のご支援・ご協力のおかげで、医学部と病院の宜野湾市西普天間住宅地区跡地への移転事業は順調に進捗しています。医学部関連の建物は、現在約4割が完成しており、令和6年10月末に竣工する予定で、医学部の開学日は令和7年4月1日の予定です。また、病院関連の建物は、現在約9割が完成しており、令和6年6月末に竣工する予定で、病院の開院日は令和7年1月6日の予定です。
最後に、抱負を述べさせていただきます。私の医学部長・医学研究科長の任期は、ちょうど医学部の移転が完了する令和7年3月末までです。移転事業が成功するように、そして医学部・医学研究科がさらに発展するように、今年も精一杯尽力して参ります。今年が、皆様にとって、健康で幸せな一年になることを衷心より祈念申し上げ、私の年頭のご挨拶とさせていただきます。
令和6(2024)年1月4日


 この度は医学部長に信任していただき、誠にありがとうございます。今後2年もよろしくお願いいたします。大屋祐輔理事・附属病院長、医学部・医学研究科執行部とともに、医学部・医学研究科・保健学研究科の発展に寄与する所存です。
この度は医学部長に信任していただき、誠にありがとうございます。今後2年もよろしくお願いいたします。大屋祐輔理事・附属病院長、医学部・医学研究科執行部とともに、医学部・医学研究科・保健学研究科の発展に寄与する所存です。